こんにちは、視能訓練士の平良です。
子どもたちの見えかたチェック(スクリーニング検査)には、屈折機器検査(他覚的検査)と視力検査(自覚的検査)があります。特に全国の自治体に広く導入されるようになったスポットビジョンスクリーナーが登場したことで、いろんなお声をいただくようになりました。
園児の見えかたチェックへのご理解を深めるために、今回はこのあたりのことをお話しします。
普及進んでます!スポットビジョンスクリーナー
以前も記事でご紹介した、スポットビジョンスクリーナー(通称SVS)は本当に素晴らしい機器です。私が勤務する小児眼科でも重宝していますが、小児科・全国各自治体の3歳児健診会場、小児科クリニックなどでも大活躍しています。
SVSは、米国ウェルチ・アレン社の屈折検査機器です。専門用語で申し訳ありませんが、各眼の屈折値/瞳孔径/PD瞳孔間距離などのほか、眼位の異常(斜視疑いなど)も検出できます。
(注)屈折値=遠視近視乱視など屈折異常の度合い


生後数か月の乳児でも、首がすわれば数秒で測定できるという汎用性がとても優れています。
SVSだけで良いのでは?の声に
さて私たちの園内スクリーニング検査では
SVS(屈折機器検査)と
ベビーアイサイト(視力検査)
の2つをおこなっています。
ときどき、

SVS(屈折機器検査)だけでよいのでは?



視力検査(自覚的検査)って面倒じゃないですか?
というご意見をいただくことがあります。
結論から言いますと、私たちは
「可能であればどちらも必要」
と考えています。
視力検査が重要な理由
①「実際の見えかた」の評価


視力検査は、子どもがどのくらい見えているのかを直接的に把握できます。これは生活の質や学習能力にも直結する重要な情報です。
スポットビジョンスクリーナー(屈折機器検査)の情報は「見えかたを阻害する要因(屈折異常値)がどれくらいあるか」を測っているものであり、視力そのものを測定しているわけではないのです。
実際にどれくらい見えているのか確認するには
視力検査しかないのです。
②年齢や発達段階に応じた確認


子どもの年齢や発達に応じた適切な視力が獲得できているかを確認できます。
たとえば、私たちが活用している
3歳児クラス/4歳児クラスで
遠見視力0.7を基準値とし、
5歳児クラスは
遠見視力1.0を基準値としています。
子どもの視力(見えかた)が年齢並みに育っているかを確認するには、やはり視力検査が欠かせないのです。
③答えかたの様子から掴む情報


私は、視力検査はコミュニケーション/対話だと考えています。
実は私たちが視力検査する場合、手元の視標はあまり見てません。
園児の様子を観察しています。
同じく視力0.7が見えているとしても、その時の答えかた,様子から得られる情報があります。
眼をグッと見開く。お顔を傾けたがる。上目づかいに見ようとする。
見えにくさのサインは視標を見ている様子から掴めることが多いのです。
なお、福岡市医師会による園内検査マニュアルによる問診票にも「園内検査の際の園児の挙動」についてのチェック項目があります。
④発達の具合を


子どもたちには豊かな個性や特性があります。
同じ4歳児クラスでも、とても恥ずかしがり屋の子、慎重に考えるような仕草の子、言葉がちょっと出にくい子、聞かれていることがまだ理解しにくいかな?という子。
検査に答える様子は出来るかぎり記録して、後日保育士さんたちに日常の様子をうかがいながら情報をすり合わせることも。
このように、視力だけでなくその園児の発達具合を確認できることも、視力検査というコミュニケーションだからこそです。
「繰り返し」が最重要
視力検査+SVS(屈折機器検査)、子どもたちの見えかたを見守るには、この双方が重要であること、ご理解いただけたでしょうか?
ただし、あくまで可能であれば、です。どうしてもどちらかしか実施できない環境もあるでしょう。片方だけでもやらないよりもやった方がもちろん有益です。
私は、最も重要なポイントは「繰り返し」にあると思っています。
3歳健診で1度やったから大丈夫。4歳時に一度視力検査したから問題ない…とは思いません。
子どもの見えかたは頻繁に変化することがあります。
また、6~8歳の精密な両眼視機能獲得までの発達において、3歳時に問題なくても、その後の正常な発達が確実とは断言できないのです。
さらに申し上げると、3歳児健診や園内検査で何らかの異常が指摘されても、その後眼科受診が100%でないことも指摘しなければなりません。たとえば私たちの園内スクリーニング検査では、のべ2,000名の園児に実施しましたが、そのうち眼科受診推奨対象児で眼科受診が確認されたのは半数ほど。
つまり指摘されても約半数が受診していないのではないかと言うデータが得られています。
見えかたを見守る = 繰り返しチェックしながら伴走する
と私たちは考えます。



みる力が発達する大切な期間。繰り返しチェックしていきたいですね。
平良美津子PROFILE


視能訓練士/みるみるプロジェクト参与
北九州市出身/大分視能訓練士専門学校卒業。北九州市立若松病院などで勤務後、医療法人大里眼科クリニックにて辰巳貞子先生のもと小児眼科を学ぶ。福岡市立こども病院眼科を経て(一社)みるみるプロジェクトを有志らと共に設立。複数の眼科クリニックで勤務しつつ後進の視能訓練士育成/異業種交流(弱視就学支援・eスポーツ研究等)/弱視早期発見活動に取り組む。
-



器械/書籍 ご寄贈のお願い-設立支援委員会より
眼科医療機関の皆様へ【ご寄贈のお願い】 学校法人国際志学園 九州医療スポーツ専門学校 理事長 水嶋章陽 北九州視能訓練学科 設立支援委員長 小児眼科医辰巳貞子 私た… -



【プレスリリース】東京八王子東ロータリークラブ3園目の視力検査キット寄贈
2025年12月、東京八王子東ロータリークラブとみるみるプロジェクトは、八王子市の敬愛こども園へ視力検査キットを寄贈いたしました。本プログラム3園目の寄贈となり、専門家と連携し弱視の早期発見・治療を支えます。これまでの活動では約5%の園児に弱視が見つかり、治療に繋がっています。お子さまの健やかな成長と「見る力」を願い、地域で温かく見守る活動を心を込めて継続してまいります。 -


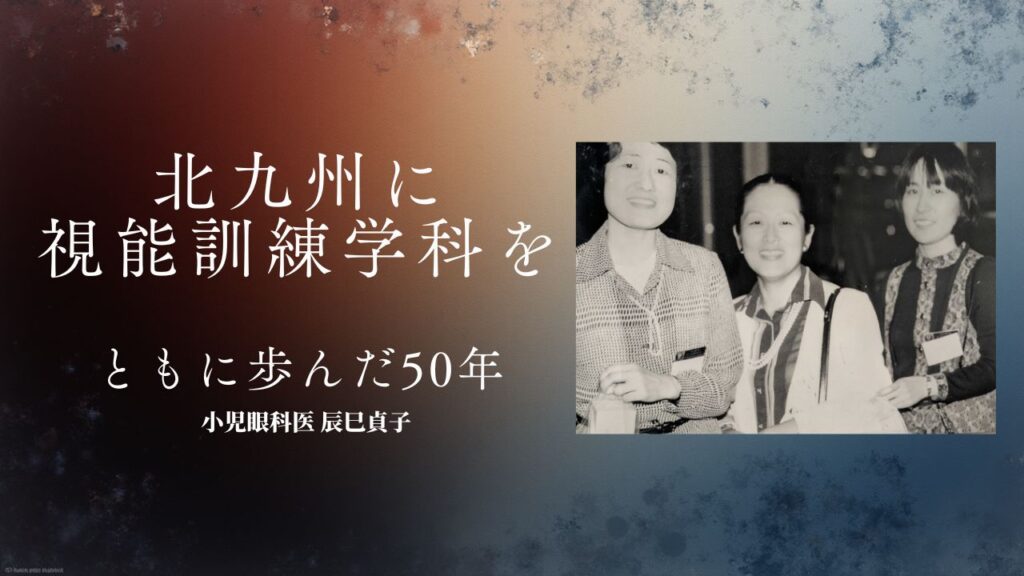
~視能訓練学科に寄せて~小児眼科医辰巳貞子先生寄稿
小児眼科医・辰巳貞子先生の、北九州で視能訓練士学科開設を望む想いを綴った寄稿。子どもの大切な「みる力」を守る専門職・視能訓練士と共に歩んで50年以上。その育成は、弱視の早期発見・治療に欠かせません。地域医療の未来を担う新たな一歩と、子どもたちの健やかな成長を願う温かなメッセージをぜひご覧ください。みるみるプロジェクトは、質の高い小児眼科医療の普及を応援しています。 -


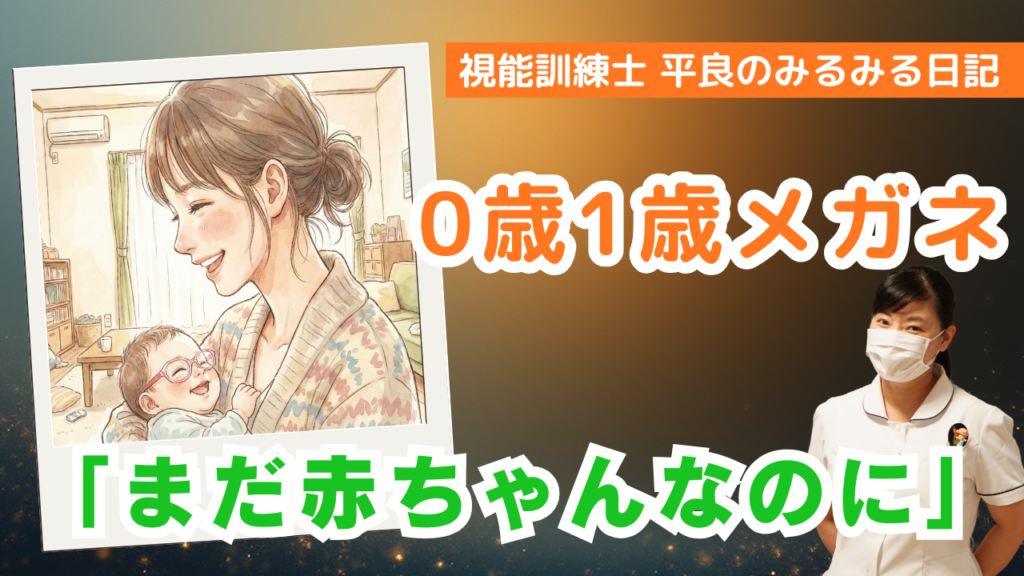
0歳1歳メガネ「まだ赤ちゃんなのに…」
【視能訓練士コラム】「0歳なのに眼鏡なんて…」と涙ぐむ保護者様へ。実は早期発見こそお子様の「みる力」を育む最高のチャンス。イヤイヤ期前の乳児期は意外にもスムーズに眼鏡に馴染める時期。不安な心を希望に変える平良流のアドバイスと、ベビー用トマトグラッシーズの選び方をご紹介します。 -


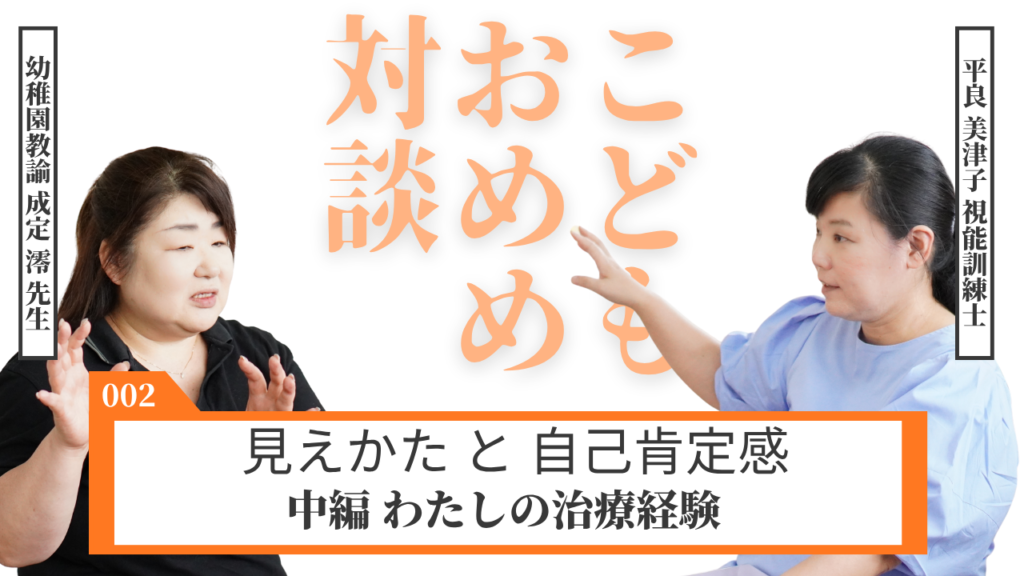
こめめ対談02~成定先生(中編)みる力と自己肯定感
子どもたちの眼を守り育てる情熱をもった方々。 前編に引き続き 星和台幼稚園(北九州市)成定 澪 (なりさだ)先生と 平良美津子視能訓練士の対談(中編)をお届けしま… -


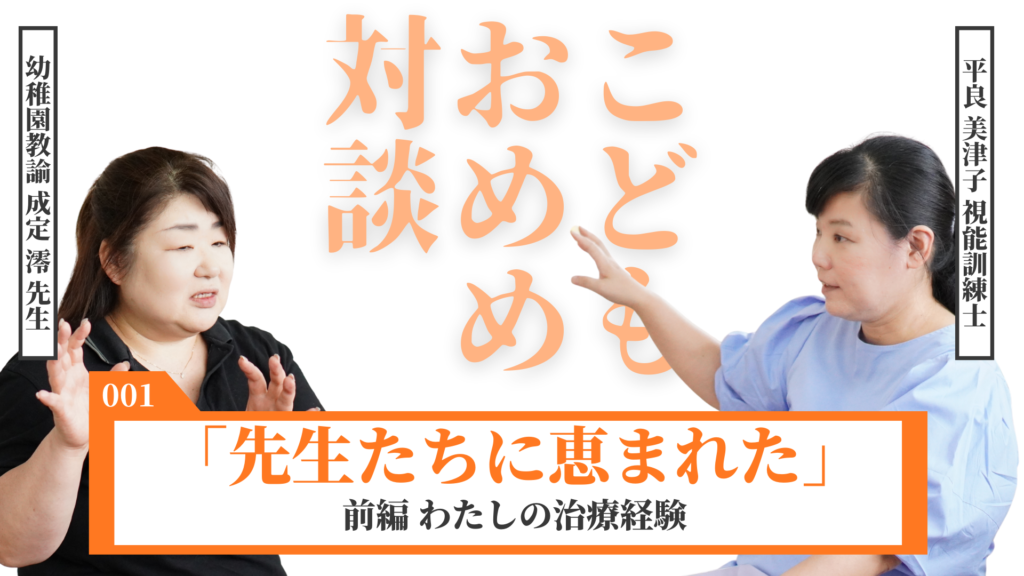
こめめ対談01~成定先生(前編)先生たちに恵まれた弱視治療
子どもたちの眼を守り育てる情熱をもった方々。星和台幼稚園(北九州市)成定 澪 (なりさだ)先生と平良美津子視能訓練士の対談(前編)です。成定先生は園児たちの目に対しても意識が高く先生ご自身の弱視治療経験も交えた有意義な対談となりました。 -



エピソード投稿しませんか~弱視治療
弱視や斜視の治療に取り組んでいる保護者様からのエピソードを募集中!眼科受診/メガネデビュー/アイパッチの思い出など応募ください -



みるみる手帳‐保護者の理解編 遠視とは?こどもめがねは?
-みるみる手帳で深めたい弱視治療保護者の理解とは。弱視治療の主な舞台は家庭にあります!遠視とは?こどもめがね装用の意味とは?手帳に関係する人々によく確認して欲しいメガネ状況とは⁉平良が解説します -



手帳の使いかた‐コミュニケーション編(眼科)
ー弱視斜視治療に寄り添うみるみる手帳。眼科との信頼関係を作るコミュニケーションツールとしての使いかたを視能訓練士平良が解説。【眼科受診メモ】ページ活用してますか?愛情豊かに観察し共有すべき情報とはー

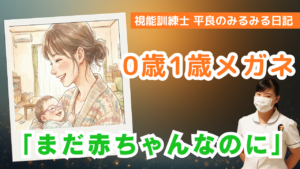
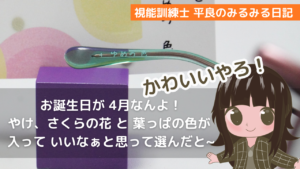





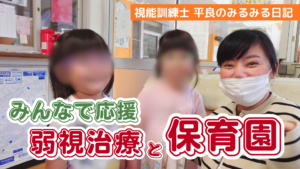
コメント